プレスリリースはこちら:崇城大学学生×早大デモクラシー創造研究所 学生の視点で参院選各党マニフェスト「できばえ」を分析 「政策実施の体制言及なく 実現可能性想像できない」分析採点1位に国民民主、2位公明・れいわ
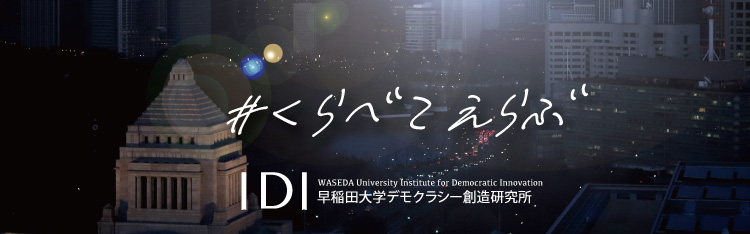
早稲田大学デモクラシー創造研究所(旧マニフェスト研究所/所長・日野 愛郎 早稲田大学政治経済学術院教授)の招聘研究員3名(青木 佑一 同研究所事務局次長、山内 健輔 同研究所選挙制度部会長、亀井 誠史)は、早稲田大学総合研究機構と包括連携協定を締結している崇城大学(熊本市)IoT・AIセンターと連携した講義「異分野イノベーション」を担当しており、この度の参議院選挙に際し、学生の視点で各党マニフェストの「できばえ」を分析するワークショップを7月15日に実施しました。
完成した「学生版マニフェストできばえチェック表」を当研究所「#くらべてえらぶ」にて公開しましたので、ご案内します。
- 当研究所が各種大型選挙で作成している「マニフェストできばえチェック表」を、初めて学生の視点でも作成しました。崇城大「異分野イノベーション(※)」の講義にて、「理念・ビジョンチーム」、「政策の具体性チーム」、「政策の実現可能性チーム」、「市民起点度チーム」の4チームに分かれチームごとに基準に沿って、10政党すべてのマニフェスト現物を見ながらできばえを分析しました。
- 下記審査項目に沿って、◎(25点 他の政党にも真似してほしい程良い)、○(15点 良い)、△(5点 悪い)、×(0点 改善を求めたい)で採点。それぞれにコメントを添えてできばえチェック表を完成させました。
- 主権者の側からも、より高い質のマニフェストを出すよう求めていく運動の起点になることを期待して実施したものです。
- 形式要件を分析評価するものであり、政策内容の賛否について明らかにしたり、特定の候補者、政党等の支持または不支持を呼び掛けたりするものではありません。
※「異分野イノベーション」
崇城大学IoT・AIセンター長である星合 隆成教授が提唱する地域活性化並びにイノベーション創発のための理論である「地域コミュニティブランド(SCB理論)」をもとにしたプロジェクトベースの講義です。3つあるコースの一つが「早稲田大学コース」です。早稲田大学コースでは、これまでに熊本県内の議会と連携して、若者の投票率向上や政治参加意識醸成に関する実践型のプロジェクトを進めてきました。
※「#くらべてえらぶ」
早稲田大学デモクラシー創造研究所が制作するマニフェスト比較ウェブサイト。前回衆院選では約20万PV(告示日〜投票日)を達成。「政党を左右で見比べる」「政党ごと」「政策ごと」の比較などができるコンテンツや、「できばえチェック表」を掲載しています。(URL:https://kurabete.maniken.online/)
※審査項目
理念・ビジョン(ありたい国の姿(理念・ビジョン・将来像)が示されているか/ありたい国の姿の根拠・着眼点が示されているか/国家としての課題が捉えられているか)
政策の具体性(政策の目標・期限・実現方法(工程)・財源などが明示されているか/達成度・成果の事後検証は可能か)
政策の実現可能性(目標・政策の実現可能性について、合理的な説明がされているか/実行体制・実行プロセスは示されているか)
市民起点度(読み手に取ってわかりやすい工夫はされているか/マニフェストの配布・周知の工夫はされているか/策定過程において国民の提案を組み込むプロセスを有しているか/市民(個人や組織)の自発的活動を推進する動機付け(インセンティブ)が織り込まれているか/マニフェストに呼応した市民活動との連携を想定しているか/異なる目的や視点で活動する市民活動同士の連携を想定しているか)
【学生版マニフェスト「#できばえチェック」 】
- できばえトップは国民民主50点、公明40点/れいわ40点、自民30点と続く
- 総合コメント「どの党も全体的にどういう未来を目指すのかというビジョンがない。政策目標があってもそれがビジョンと繋がっていない。また、目標に対する期限が明示されている政党が少なく、書かれている政策を実施するための体制や人材、ルールの整備などの言及がないため実現可能性を想像できない。政権与党の自民、公明は党内や近くの人々だけで完成させたようなイメージを持ったが、新しい政党などは市民との連携を意識して作ったことがマニフェストから感じ取ることができた。」




